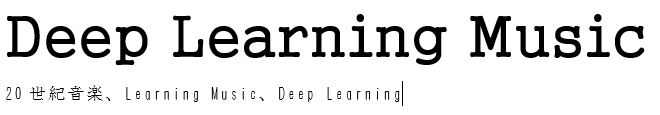セコンドライン(Second Line)は、アメリカ・ルイジアナ州ニューオーリンズにおける伝統的なブラスバンド・パレードの一形態で、「ファーストライン(First Line)」と呼ばれる主催者やブラスバンドに続いて、一般の参加者(セカンドライン)が音楽に合わせて踊りながら行進する文化です。このスタイルの踊りは「セカンドライニング(second-lining)」と呼ばれ、傘やハンカチを振りながら自由にステップを踏むのが特徴です。ニューオリンズ・セコンドラインというと、この伝統的なパレードのことを言う 場合と、そのパレードで演奏される音楽から生まれた独自のリズムパターンやそのグルーブのことを言う場合があります。
セコンドライン・リズムとグルーブ
このリズムは、「セカンドライン・リズム」や「セカンドライン・ビート」とも呼ばれ、ニューオーリンズのジャズ、R&B、ファンクなど、様々な音楽ジャンルに重要な影響を与えています。やや大げさに言ってしまうと、20世紀以降世界を席巻した黒人音楽のグルーブの原点だと言えます。
- アフリカのポリリズムとヨーロッパの音楽理論が融合した独特のグルーヴを持つ。
- シャッフルがしっかりハネていないような、微妙に跳ねたり引きずるような、ウネリのあるビート感が良く知られています。バーナード・パーディやジェフ・ポーカロでよく知られたあのウネリのあるグルーブの源流です。
- 偶数小節の4拍目に特徴的なアクセント(ビッグ・フォー)がある一方で、即興性が最大限に発揮されます。
バーナード・パーディ (Bernard “Pretty” Purdie)
バーナード・パーディは、1939年6月11日、アメリカ合衆国メリーランド州エルドン生まれの、世界で最も録音されたドラマーの一人として知られる伝説的なドラマーです。その独特のグルーヴと「パーディ・シャッフル」に代表される独自のスタイルで、R&B、ファンク、ソウル、ジャズ、ロックなど、数えきれないほどの楽曲に貢献してきました。特に、彼が生み出した独特のシャッフル・リズムは「パーディ・シャッフル」として知られ、多くのドラマーに影響を与えました。このリズムは、ハイハットのクローズド・オープンとゴーストノートを巧みに組み合わせ、ルーズでありながらも強烈なドライブ感を持つのが特徴です。YouTubeでは彼が「セコンド・ライン・グルーブ」を実演している映像が見られます。
Bernard Purdie – Second Line Rhythm
ビッグ・フォア~スイングの要
4拍目を特に重視し、次の1拍目に向かって微妙な「タメ」と「推進力」を生み出すリズムの感じ方として「ビッグ・フォア」が使われることがあります。これは、ジャズの伝統的な4ビートにおける非常に洗練されたリズムの解釈であり、演奏をよりダイナミックで魅力的なものにするための鍵となります。ジャズ系のドラム講師の人たちが、しばしばこの「ビッグ・フォア」を口にします。スウィングの「コツ」として、あるいはグルーブの「鍵」として。
ジャズのスウィングは、2拍目と4拍目の「バックビート」が強調されることが特徴の一つですが、それだけでなく、4拍目(あるいはその裏拍)でリズムをわずかに「溜める」感覚を持つことで、次の1拍目(拍の頭)へのエネルギーが凝縮され、より力強く、そして心地よいスウィング感が生み出されます。 これは、単に楽譜通りに音符を並べるのではなく、拍の間に「間(ま)」や「ノリ」といった微妙な揺らぎを加えることで、音楽に生命力を与える感覚です。4拍目をしっかりと感じることで、音楽が「前に押し出される」ような推進力を持ち、聴衆が自然と身体を揺らしたくなるようなグルーヴが生まれます。
近くのルーツ ニューオリンズ
ニューオリンズのファンクに代表される、ダブルバックビートというのがあります。これはMetersのCissy Strutを聴いてもらえばまさにそのズバリのグルーブです。形式的に言ってしまえば16ビートにおける4拍目の裏にアクセントのニュアンスが来ます。実はこれは16ビートのテンポを倍速にした時の4ビートのビッグ・フォアが、偶数小節に入ってくる、というように感じることができます。つまりテンポを4ビートで感じた時に、1小節おきにビッグ・フォアが来る、と捉えればいいのです。
これはかの「バックビートおじさん」もどこかで言及していたのですが、バックビート界隈のみならず、4ビートスウィング界隈でもちょっと知られた話です。
言ってしまうと、16ビートもその倍速の4ビートも、ビッグ・フォアの4拍目に向かって(狙って)吸い込まれるように落ちていくんですね。これが「ポケット」であり「重心」という感覚の大元である、と言ってしまっていいと思います。
20世紀アメリカの黒人音楽における、近くのルーツがニューオリンズで、遠いルーツがアフリカ西海岸であることは異論を待たないと思います。